マンション管理組合の理事をやりたくない組合員ばかりの管理組合にお勧めする管理体制

🎬 動画解説(約6分30秒)
🎥映像で理解したい方は、動画解説をこちらから再生できます。
🎧 音声解説(約6分)
👂 耳で理解したい方は、対話式の音声解説をこちらで再生できます。
区分所有マンションを購入すると、その瞬間から自動的に「区分所有者で構成される団体=管理組合」の一員となります。
そして、管理組合設立総会の決議を経て正式に組合員となるのが一般的です。
この「管理組合の組合員」という立場は、マンションを売却して区分所有者でなくなるまで続き、途中で脱退することはできません。
いわば“終身会員”のようなものです。
さらに、多くの管理組合では、理事や監事といった役員を数年ごとに持ち回りで担当する「輪番制」を採用しています。
しかし実際には、「できるだけ理事にはなりたくない」「責任が重そうで不安」という理由から、役員就任を避けたいと考える組合員が少なくありません。
本記事では、そのように“理事をやりたくない組合員ばかり”という現実を抱える管理組合に向けて、無理なく運営できるお勧めの管理体制について解説します。
目 次
Toggle理事をやりたくない組合員ばかりの管理組合にありがちな管理状態

理事などの役員が毎年のように交代し、理事会も一度も開かれないまま、形式的に年1回の通常総会だけを開催している・・・
そんな管理組合は、決して珍しくありません。
総会には建物管理会社の担当者と、名ばかりの理事長だけが出席しているというケースも見られます。
特に、各住戸を賃貸に出している所有者が多く、マンションに実際に住んでいない区分所有者が多い“賃貸化率の高いマンション”ほど、この傾向は強まります。
このような状態では、管理組合の運営が事実上、建物管理会社任せになってしまいがちです。
結果として、建物管理会社の都合に沿った運営が進み、管理組合にとって不利益となる可能性も高まります。
建物管理会社は、あくまで営利企業として管理委託契約に基づき業務を行っています。
そのため、管理組合の財政が厳しくなっても、自社の管理委託費を自ら削減するようなことはほとんどありません。
むしろ、管理費や修繕積立金の値上げを提案しつつ、自社への委託費用の引き上げを打診してくることさえあります。
さらに、理事会が機能していないと、日常清掃の質や設備点検の実施状況、居住者のルール・マナー違反への対応といった細部まで確認することができません。
その結果、「本当に適切な管理が行われているのか」を誰も判断できない。
そんな“形だけの管理”に陥る危険性が高まっていくのです。
理事をやりたくない理由とは?

管理組合で理事のなり手がいない。
この問題は、どのマンションでも少なからず共通しています。
もちろんマンションの規模や居住者層によって事情は多少異なりますが、多くの場合、次の4つのいずれかの理由に当てはまります。
1.無関心(面倒くさい)
「理事になっても報酬が出るわけではないし、正直、面倒くさい」
こうした声は非常に多く聞かれます。
管理組合の活動に興味がなく、「建物管理会社や誰かがやってくれればいい」と考えてしまうパターンです。
結果として、管理に主体的に関わる人が減り、組合運営の形骸化につながっていきます。
2.時間がない
共働き世帯が増え、本業や子育てに追われるなかで、「理事会に参加する時間がない」という人も多いでしょう。
とくに平日夜や休日に理事会が開かれると、時間的な負担を理由に辞退するケースが目立ちます。
3.よくわからない
「理事になっても、何をすればいいのか全くわからない」
「どんな判断をすれば“正しい管理”なのか不安」
この“わからないことへの不安”も大きな壁です。
マニュアルや引継ぎ資料が整っていない管理組合では、経験者の勘頼みになり、新任理事が萎縮してしまう傾向も見られます。
4.身体的理由
居住者の高齢化が進むマンションでは、「体力的に理事会活動が難しい」「会議出席や資料作成が負担」という理由も少なくありません。
役員を務めたくても現実的に難しいというケースです。
理事長を外部の専門家に委託する

マンションの管理運営には、法的な知識や建物・設備の理解、会計処理など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。
そのため、一般の組合員だけで「何が適切で健全な管理なのか」を判断するのは、決して簡単ではありません。
そこで私が強くお勧めしたいのが、建物管理会社とは独立した立場にある外部の専門家(マンション管理士など)へ支援を依頼する方法です。
外部の専門家の活用には、大きく2つのパターンがあります。
【1】顧問として支援を受ける
1つ目は、専門家を管理組合の顧問として迎え、コンサルティング契約を結ぶ方法です。
理事会のメンバーが一定の意欲を持ち、主体的に活動している管理組合では、この形が特に効果的です。
専門家が理事会に同席し、議題に対して助言や改善提案を行うことで、意思決定の精度が高まり、健全な管理が進みます。
しかし、理事会がほとんど機能しておらず、理事自身が管理に無関心な場合には、この方法だけでは十分な効果を発揮できません。
顧問はあくまで助言者であり、実質的な決定権や執行権限を持たないためです。
【2】理事・理事長として専門家に就任してもらう
2つ目の方法は、外部の専門家に理事あるいは理事長として正式に就任してもらうという形です。
この場合、専門家は理事会の一員として発言権・決定権を持つため、実質的に管理組合の運営を主導できます。
これにより、理事会が主体的に動く体制が整い、長年滞っていた課題の解決や、収支バランスの改善が実現しやすくなります。
もちろん、このような外部委託方式を採用する場合には、建物管理会社への管理委託費とは別に、専門家への報酬(委託費用)が発生します。
しかし、専門的な知見をもとに適正な契約見直しや費用削減を行うことで、結果的に委託費用以上の収支改善を実現できるケースも少なくありません。
【行政の支援制度も活用しよう】
なお、外部専門家に相談する場合には、一定の費用がかかるのが一般的です。
ただし、区市町村などの地方自治体では、無料でマンション管理士を派遣する制度を設けているところもあります。
まずは、お住まいの自治体の制度を確認し、活用してみるのも良いでしょう。
まとめ

理事のなり手がいない・・・
これは多くのマンション管理組合が直面している共通の課題です。
無関心、忙しさ、知識不足、そして高齢化。どの理由も、決して誰か一人を責められるものではありません。
しかし、理事会が機能しないままでは、建物の維持管理や会計の健全性が失われ、結果的に資産価値の低下にもつながります。
大切なのは、「誰かがやらなければならない」ではなく、「どうすれば無理なく続けられる体制を作れるか」という発想に変えることです。
その解決策のひとつが、外部の専門家(マンション管理士など)をうまく活用することです。
顧問としての助言を受ける方法もあれば、理事や理事長として実務を担ってもらう方式もあります。
専門家が関わることで、理事会が停滞するリスクを減らし、建物管理の質と透明性を高めることができます。
管理組合の運営は、決して「誰かの善意」や「時間のある人」に頼るべきものではありません。
限られた人員でも安定的に運営できる仕組みを整えることこそが、これからの時代に求められる“持続可能なマンション管理”です。
まずは、自治体の無料相談制度などを活用し、外部専門家への相談から一歩を踏み出してみてください。
その一歩が、管理組合全体の安心とマンションの未来を守る大きな転換点となるでしょう。
本日も読んでいただき、どうもありがとうございました。
2.jpg)

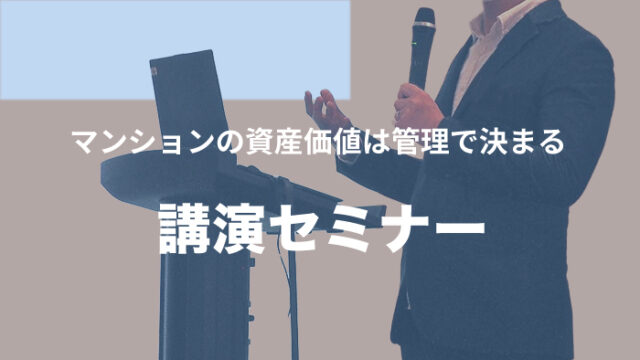


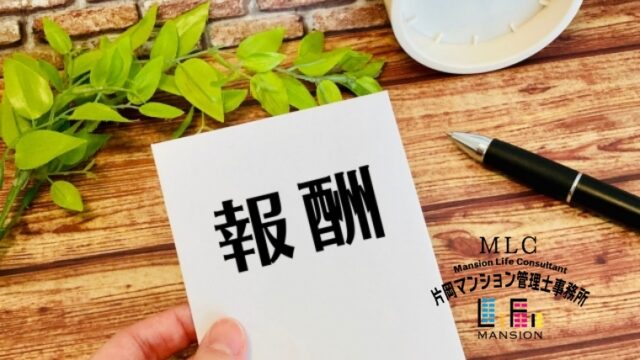


-320x180.jpg)

.jpg)



2.jpg)




