管理会社に任せて安心? 管理業者管理者方式の真実と課題~理想論を語るだけでは通用しない時代~
.jpg)
🎬 動画解説(約6分30秒)
🎥映像で理解したい方は、動画解説をこちらから再生できます。
🎧 音声解説(約8分)
👂 耳で理解したい方は、対話式の音声解説をこちらで再生できます。
マンション管理の現場では、管理組合に理事会を設置せず、管理業者に管理者の役割を一任する「管理業者管理者方式」の導入が、近年増加傾向にあります。
特に、区分所有者の高齢化や賃貸化率の上昇により理事の担い手不足が深刻化しているマンションでは、「役員が不要」「手間がかからない」といった理由から、この方式を採用するケースが目立っています。
「管理業者管理者方式」とは、管理規約に基づき、管理組合の総会で管理業者を管理者として選任し、その業者が組合の代表者として管理運営全般を担う体制を指します。
本記事では、管理組合が管理業者管理者方式の採用を検討する際に留意すべきポイントやメリット・デメリットについて解説し、判断の参考としていただける内容をお届けします。
目 次
Toggleなぜ今、管理業者管理者方式が増えているのか?
本来、理事長をはじめとする区分所有者による役員が担っていた管理運営の職務を、外部の管理業者が代行するのが「管理業者管理者方式」です。
たとえば、総会の開催案内や議案書の作成、業者との契約交渉、会計処理など、実務の大部分を管理者として選任された管理業者が担うことで、区分所有者の負担は大幅に軽減されます。
「プロに任せれば安心」「高齢者や無関心な組合員の多い管理組合にはありがたい」といった声も聞かれますが、果たして本当にそうでしょうか。
この方式が広がりを見せている背景には、2000年代以降に顕在化した管理組合の「人材難」があります。
かつては、組合員同士のつながりの中で自然と役員が決まるケースも少なくありませんでしたが、都市部の分譲マンションでは組合員同士の関係が希薄化し、「誰もやりたがらない」状態が常態化しています。
さらに、賃貸住戸の増加により、区分所有者である組合員がそのマンションに居住していないケースが多くなると、さらに管理への関心も薄れがちになっていきます。
このような状況のなか、「管理業者管理者方式」は、理事のなり手不足という深刻な課題に対する“最後の選択肢”として採用されるケースが増えているのです。
外部委託のワナ:見えないリスクと透明性の問題
一見すると、管理業者管理者方式は、管理のプロに業務を任せられる理想的な仕組みに思えるかもしれません。
しかし実際には、「見えないところで進行する劣化」も存在します。
まず第一に、管理業者管理者方式では情報の非対称性(管理会社だけが契約や支出の詳細を把握し、管理組合側には見えにくい構造)が発生しやすくなります。
理事会方式では、役員が管理会社からの報告を受け、内容を確認・検討した上で意思決定を行うというチェックの仕組みがあります。
しかし、管理者方式では、管理者が報告と意思決定の両方を一手に担うため、その過程がブラックボックス化しやすくなります。
その結果、総会に提出される議案も「形だけの可決事項」となりがちで、区分所有者の関与度は徐々に低下していきます。
加えて、契約内容や支出の監視機能も弱体化するリスクがあります。
たとえば、管理会社が自社グループ企業に対して、高額な清掃や修繕工事を発注していたとしても、それを精査・是正する管理組合の機関がなければ、コストや品質が適正かどうか判断する術がありません。
さらに、管理者が本来個人としての責任を負うべき立場であるにもかかわらず、実際には「会社としての管理会社」に業務を一任し、自らの責任をあいまいにするようなケースも考えられます。
このような利益相反を伴う不透明な運営はトラブルの火種となるでしょう。
実際、管理者方式を採用しているマンションの中には、数年にわたり会計上の不正や不明朗な支出が放置され、気づいたときには修繕積立金が大幅に減っていたという事例もしばしば耳にします。
このように、理事会という「抑制と監督の機能」が失われれば、内部監査も形骸化し、管理組合の健全な運営を維持することが難しくなります。
もちろん、管理会社が誠実かつ透明性の高い運営を行っていれば、深刻な問題には至らないケースもあるでしょう。
しかし、組合側にその誠実さを検証する手段や仕組みがないまま、ただ依存してしまう構造そのものが、実は最大のリスクであると言えるのではないでしょうか。
持続可能な管理体制とは?
管理業者管理者方式は、理事のなり手不足といった現実的な課題に対応する選択肢として注目されています。
しかしながら、制度そのものに限界があることを理解しておく必要があります。
たしかに「役員の担い手不足を補う手段」としては一定の効果がありますが、中長期的な視点で見れば、組合運営の主体性や財務の健全性をどう確保していくかという点で、大きな課題を残しています。
では、これに代わる現実的な選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか。
その一つが、「外部専門家との協働」というモデルです。
たとえば、マンション管理士などの第三者を外部顧問として迎え入れ、役員は最低限の意思決定機能のみを担いながら、日常業務の相談や監査、助言を外部専門家から受けるという体制です。
この方式であれば、ガバナンスを保ちつつ、役員の負担を軽減することが可能です。
また、デジタルツールの活用によって、意思決定の透明性や記録性を高めることも重要です。
たとえば、オンライン理事会の実施や電子議決権の導入によって、遠方に居住する区分所有者や高齢者も、無理なく意思表示や役員活動に参加できる環境が整います。
これにより、役員選出の候補者層も広がります。
さらに、理事会方式と管理者方式の「ハイブリッド型」も、有効な選択肢のひとつです。
具体的には、たとえば最低限の理事(3名程度)を選任し、日常業務の多くは管理会社と外部顧問に委託するという仕組みです。
このようなモデルであれば、管理会社の独断を防ぎながら、組合としての監視・評価機能を維持することが可能となります。
最終的に問われているのは、「誰のためのマンション管理か?」という根本的な視点です。
管理者方式に過度に依存すれば、区分所有者としての責任や関心が希薄となり、結果的にマンションの資産価値や住環境の質が損なわれてしまうおそれがあります。
一人ひとりの無関心が、やがて「管理不全」という深刻な問題へとつながりかねない時代です。
だからこそ、管理者方式を導入する際には「すべてを任せる」のではなく、「組合として見守り、支える責任」を果たす姿勢が求められるのではないでしょうか。
「理想論では動かない」マンション管理の現実と選択肢
これまで、管理業者管理者方式にはリスクがあり、組合員である区分所有者一人ひとりが管理意識をもち、責任を果たす姿勢が大切だと述べてきました。
しかし、これは従来までの理想論と言わざるを得ないのが現実です。
たしかに、管理業者管理者方式には課題もありますが、現実的には「自ら運営することを望まない、あるいはできない」管理組合が増えているのが事実なのです。
高齢化による身体的負担、仕事や家庭の多忙、さらには居住者と非居住者の組合員の混在など、多くのマンションで「理事をやりたくてもやれない」「関心はあるが関与したくない」という空気が常態化しています。
このような背景のもとで、「誰かが適切にやってくれるなら自分は関与したくない」という層が多数派となりつつあるのが、現在の管理組合のリアルです。
そのような中で、「管理意識を高めよう」といった啓発的なアプローチは、ほとんど効果を発揮していないのが現場感覚ではないでしょうか。
理想論として語られがちな「全員参加型の組合運営」は、現実には実現困難であり、むしろ100年経っても変わらない「幻想」に近いかもしれません。
だからこそ、これからのマンション管理は、区分所有者である組合員に対して明確な選択肢を提示する必要があります。
◆選択肢は以下の三つしかない
①「お金を出してプロに任せる」
・管理業者管理者者方式やマンション管理士などの外部専門家や管理会社に管理者業務を委託する。管理組合は最低限の監視と意思決定にとどめる。コストが発生する代わりに、手間と時間を大幅に節約できる。
②「自ら役員として関与する」
・理事会方式などで区分所有者が主体的に管理を担うことを維持していく。ただし人材確保が前提で、精神的・時間的負担が避けられないことを理解する必要がある。
③「何もしない=管理不全に陥る」
・管理組合の運営が機能しなくなり、設備は老朽化し、合意形成も困難となり、結果として資産価値が急落する。いわゆる“スラム化マンション”への入り口となっていく。最悪の場合、行政による代執行で建物の取壊しが行われることもあり、その費用は最終的に各区分所有者が負担しなければならないという現実を認識しておく必要がある。
まとめ
マンションの管理活動は「誰かがやってくれるはず」と思っているうちに、管理不全は静かに進行していきます。
多くの区分所有者は、「理事はやりたくない」「管理には関わりたくない」と思いつつも、「誰かがちゃんとやってくれるならそれでいい」と考えています。
これは、無関心ではなく、「関わらない」という意思を持った無関心、いわば「意思ある無関心」と呼ぶべき状態です。
しかし、誰もがその立場を選び続ければ、マンションの管理は次第に機能を失い、やがて深刻な管理不全に陥ってしまいます。
だからこそ今、組合員一人ひとりが「お金を払って任せるのか」「自ら関与するのか」、あるいは「何もしないまま管理不全になり、最終的な責任をとっていくのか」という『責任ある選択』を迫られているのです。
理想論を語るだけでは、もはや通用しません。
限られた人材・予算・関心の中で、いかに持続可能で現実的な管理体制を構築するか。
それこそが、これからのマンション管理における最も重要で本質的な課題なのです。
組合員の皆さま一人ひとりが『責任ある選択』をしていただき、マンションの適切な管理とその維持・向上を実現していかれることを強く願っております。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。
2.jpg)

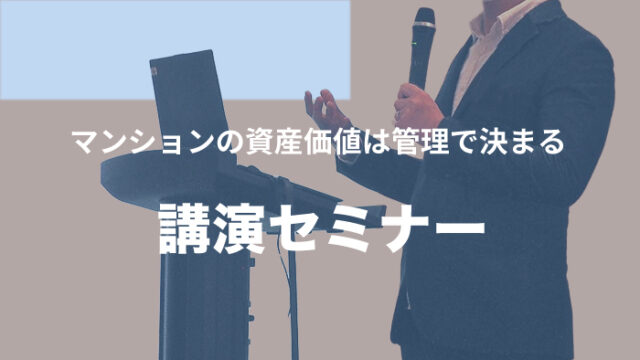







.jpg)



2.jpg)




