第4回 2026年4月1日施行 区分所有法改正【第一章 建物の区分所有 第五節 規約及び集会】のポイント

約20年ぶりとなる大幅な区分所有法改正が、2025年5月に公布され、2026年4月1日に施行されます。
今回の改正では、区分所有者に新たな義務や管理上のルールが加わりました。
本コラムでは、「第一章 第五節 規約及び集会」の改正条文を全文掲載し、その内容と管理運営への影響を解説します。
目 次
Toggle規約の設定、変更及び廃止
改正条文:第三十一条1項・2項
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
📝解説
従来は「区分所有者総数および議決権総数の各4分の3以上」の賛成が必要で、規約改正のハードルは非常に高いものでした。
今回の改正では、まず「区分所有者と議決権の過半数」が出席していることを定足数とし、そのうえで 出席した区分所有者および出席議決権の各4分の3以上の賛成 によって成立する仕組みに改められました。
これにより、総会の出席率が低いマンションでも、一定の定足数を満たせば規約改正が可能となり、現実的な運営がしやすくなります。
さらに、一部共用部分に関する規約改正については「4分の1を超える反対」があると成立しない仕組みが導入されました。
規約の保管及び閲覧
新設条文:第三十三条3項
第三十三条3
規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。
📝解説
規約の保管・閲覧方法に「電磁的方法による情報提供」が追加されました。
改正条文:第三十三条4項
第三十三条4
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
📝解説
規約の保管場所(例:管理員室、掲示板など)を必ず掲示しなければならない条項は3項から4項に移動しました。
集会の招集
改正条文:第三十四条3項・5項
第三十四条
3 区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
📝解説
これまでどおり、区分所有者および議決権の「5分の1以上」で集会招集を請求できます。
規約でこの定数を減らせる点も従来と変わりません。
今回の改正で新たに明記されたのは、「議決権を有しないものを除く」 という要件です。
つまり、議決権のない区分所有者は定数算定から外されることになり、実態に即した柔軟な運用が可能となりました。
招集の通知
改正条文:第三十五条1項
第三十五条1
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
📝解説
集会招集通知に「議案の要領」の記載が義務化され、「議決権を有しないものを除く」が追加されました。
また、期間の「伸縮」が「伸⾧」へ文言修正が行われました。
削除条文:第三十五条5項
📝解説
第三十五条5項は特定の決議事項の場合に議案の要領を通知する旨の規定が第一項に統合され削除されました。
招集手続の省略
改正条文:第三十六条
第三十六条
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
📝解説
招集手続省略の同意要件において、「議決権を有しないものを除く」が追加されました。
所在等不明区分所有者の除外
新設条文:第三十八条の二
第三十八条の二
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
2 前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。
3 一般区分所有者の請求により第一項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
📝解説
この条文は、所在不明の区分所有者がいて総会が進まない問題を解決するために新設されました。
◆裁判所の判断で除外可能
区分所有者や管理者が申立て、所在不明と認められれば、その人は議決権を持たない扱いとなります。
◆議決権の扱い
裁判で所在不明とされた人は総会で議決権を行使できません。ただし、建物滅失後の敷地利用権など特定の場合は例外あり。
◆通知・掲示の義務
一般区分所有者が申立てた場合は、結果を管理者へ通知し、管理者がいなければ建物内に掲示する必要があります。
議事
改正条文:第三十九条1~3項
第三十九条
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
📝解説
集会決議の要件に「出席区分所有者とその議決権の過半数」と明確化され、「議決権を有しないものを除く」が追加されました。
2 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。
📝解説
書面・代理人による議決権行使が、「出席区分所有者数・議決権数に算入されることが明記」されました。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして、同項後段の規定を適用する。
📝解説
電磁的方法による議決権行使が、書面による行使と同様に出席区分所有者数・議決権数に算入されることが明記されました。
議決権行使者の指定
改正条文:第四十条
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
📝解説
議決権行使者の指定において、共有者の「持分の価格に従い、その過半数」で定めることが追加されました。
占有者の意見陳述権
改正条文:第四十四条2項
第四十四条2項
前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
📝解説
占有者の意見陳述権行使時の掲示内容に「議案の要領」が追加されました。
書面又は電磁的方法による決議
改正条文:第四十五
第四十五条
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
📝解説
書面・電磁的方法による決議において、「議決権を有しないものを除く」が追加されました。
次回のコラムでは、「第一章 第六節 所有者不明専有部分管理命令」の改正内容をご紹介していきます。
条文の正確な理解は、健全な管理運営の第一歩です。
本記事該当の区分所有法(2026年改正版)現行・改正比較表(PDF)
👉こちらからダウンロード
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
2.jpg)

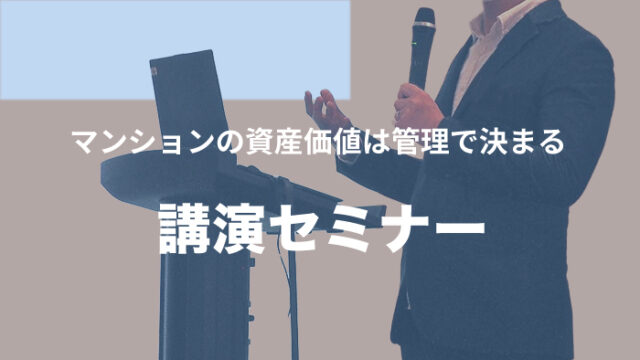


-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-pdf.jpg)


.jpg)



2.jpg)




