部屋の窓ガラスが自然に割れた!?この場合の修理費用は管理組合負担?それとも居住者負担?

🎬 動画解説(約8分20秒)
🎥映像で理解したい方は、動画解説をこちらから再生できます。
🎧 音声解説(約8分30秒)
👂 耳で理解したい方は、対話式の音声解説をこちらで再生できます。
分譲マンションでときどき起きるトラブルのひとつが、住戸内の窓ガラスが突然割れるという現象です。
何かをぶつけたわけでもなく、地震や台風の影響もない。
それでもある日突然「パリンッ」と音を立ててひび割れが広がる。
住民からは「自然に割れたのだから、管理組合が修理するのでは?」という声が上がりますが、実務では負担区分をめぐって対立が起こる場面も多く見られます。
目 次
Toggle窓ガラスは共用部分?専有部分?
まず、前提として押さえておきたいのが、マンションの窓ガラスは共用部分であるという点です。
国土交通省の「標準管理規約」においても、外壁やサッシ・窓ガラスは共用部分に分類されており、区分所有者が勝手に交換や改造を行うことはできません。
しかし、「共用部分=常に管理組合が修繕費を負担する」わけではありません。
実際には、破損の原因や居住者の使用状況によって、負担者が変わるケースが多いのです。
熱割れとは何か?割れるメカニズムとリスク要因
自然に割れる窓ガラスの多くは、「熱割れ」と呼ばれる現象によるものです。
🔍熱割れとは?
窓ガラスの一部に太陽光が当たって高温になる一方、周囲が冷えたままの状態が続くと、ガラス内に応力が生じてひび割れが発生します。
特に冬場の暖房使用や、夏場の冷房と直射日光の組み合わせなど室内外の温度差で発生しやすくなります。
💥割れやすくなる要因:
・カーテンを閉め切っている(冬場)
※夏場は逆にカーテンを閉めた方が割れにくい
・窓に遮熱フィルムを貼っている
・家具を窓際に密着させている
・ワイヤー入り(網入り)ガラスである
なかでも網入りガラスは、内部に金属ワイヤーがあることで熱応力が集中しやすく、もっとも熱割れしやすい構造として知られています。
判例と実務の傾向:所有者負担とされる理由
過去の判例では、窓ガラスが共用部分であっても、割れた原因が区分所有者の室内環境に起因する遮熱フィルムや家具配置が影響したといった事情がある場合には、「区分所有者の責任により費用負担すべき」と判断されているようです。
🧑⚖️判例例(東京地裁・平成29年など)
熱割れは通常使用に伴うものとして、専用使用権者において費用負担するべきと結論されています。
つまり、「自然現象」でも、居住者の使用態様と結びつけば“自己責任”と判断されやすいのです。
異常気象と不可抗力の考え方。将来の判例は変わる?
ただし、近年の異常気象、猛暑や寒暖差の激化を背景に、「これはもはや居住者の責任ではなく、予測困難な不可抗力では?」といった考え方も出てきています。
今後、もし訴訟となった場合、裁判所が異常気象を“通常予見できない事象”と捉える建物の設計・耐久性に疑問を呈するといったケースでは、管理組合の責任が一部認められる可能性も否定できません。
特に、同様の熱割れが複数戸で発生している場合などは、構造的な問題と見なされるリスクもあります。
管理規約の明文化による調整の可能性
実務上重要なのが、「あいまいなままにしないこと」です。
過去の判例では、管理規約に明記されていなかったことでトラブルや訴訟の火種になったとも考えられます。
逆にいえば、管理規約や細則で「熱割れ等の自然破損は管理組合で修繕する」と明文化しておけば、それに従った対応が可能になるものと考えます。
✍管理規約・細則の記載例:
「窓ガラスの熱割れ等の自然破損については、専用使用権者の明確な過失が認められない限り、管理組合が修繕費用を負担するものとする。」
このような文言を加えることで、判断の一貫性と居住者への公平な対応が可能になります。
トラブルを防ぐには“線引き”の明確化を
熱割れによる窓ガラス破損は、今後も増加が予想される“新たな管理リスク”です。
従来の判例では居住者負担とされてはいるものの、異常気象や社会状況の変化を踏まえると、今後の判断が変化する可能性も十分にあります。
だからこそ、管理組合としてはあらかじめ管理規約や細則でルールを明確にしておくことが重要です。
居住者と管理組合の信頼関係を保ち、トラブルを未然に防ぐためにも、ルールの「見える化」と「納得感」のある運用体制の整備が求められます。
まとめ
窓ガラスの突然の破損は、原因が見えにくいために管理組合と居住者の間でトラブルになりやすい事例のひとつです。
共用部分であっても、室内環境や使用状況に起因する「熱割れ」であれば、従来の判例では専用使用権者の負担とされています。
しかし、異常気象の常態化やガラス構造の特性を踏まえると、今後は判例や実務の運用に変化が生じる可能性も否定できません。
こうした曖昧な領域だからこそ、管理規約や細則でルールを明文化し、「誰が・どのようなときに・何を負担するのか」という線引きを明確にしておくことが、将来的なトラブル防止と納得感のある管理運営に不可欠となるでしょう。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。
2.jpg)

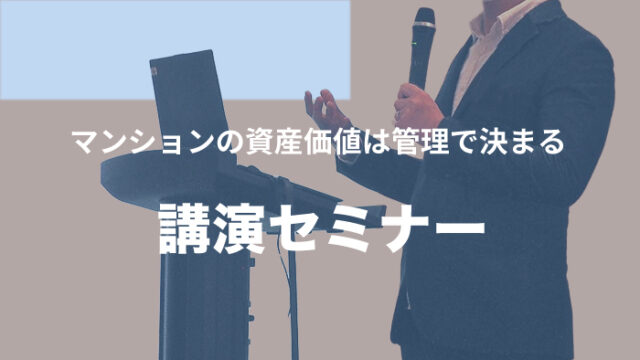



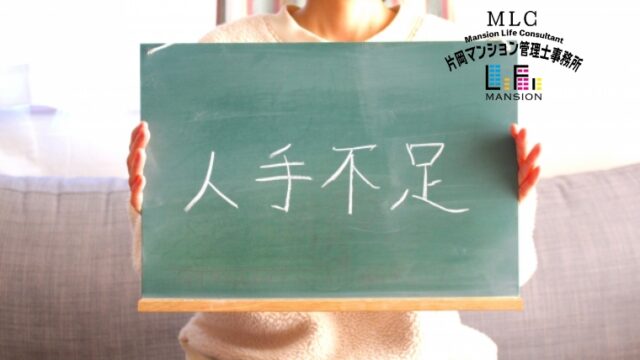



.jpg)



2.jpg)




